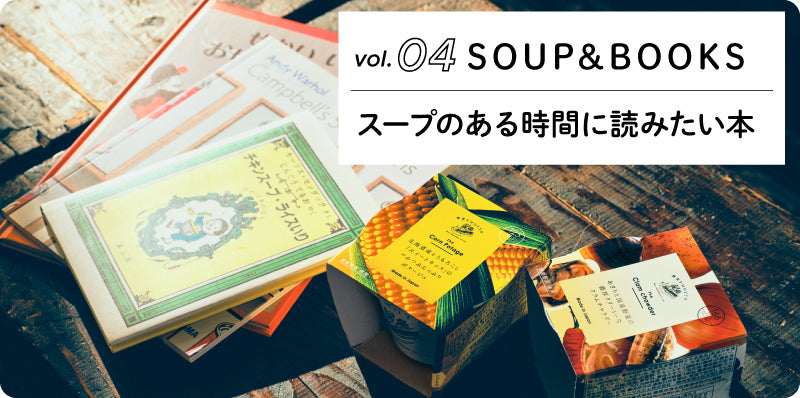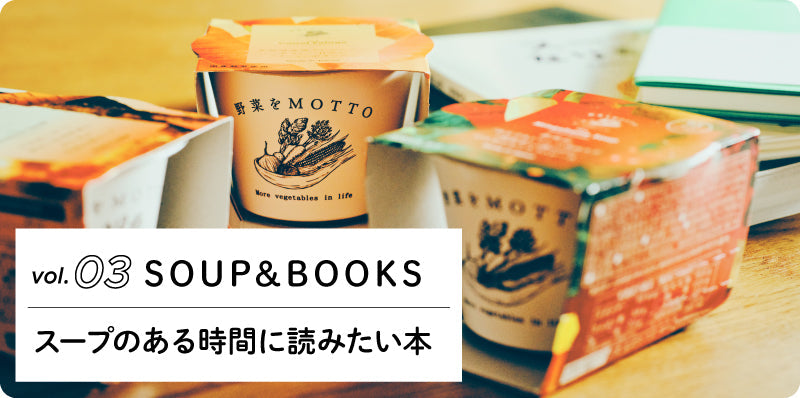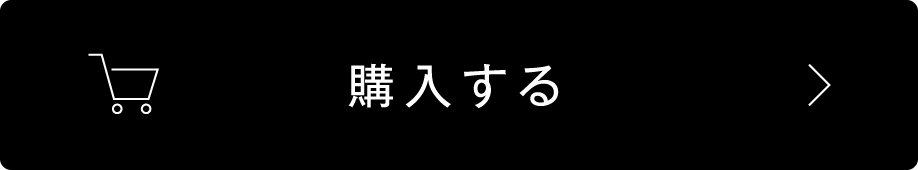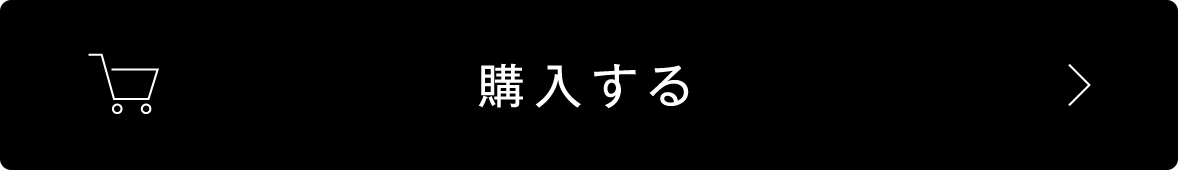スープは、誰かを想う“ケア”の料理|永井玲衣さんとスープについて考えてみる vol.01

永井玲衣さんと
スープについて考えてみる
スープは、身体をあたためるだけの料理ではありません。誰かと囲んだり、ひとりで静かに飲んだり。忙しさの合間に、ふっと心をゆるめてくれる。そんな日々のなかのスープに、私たちはどんな想いを託しているのでしょうか。哲学者・永井玲衣さんに、「スープ」と「問い」について伺いました。3つのエピソードを通して見えてきたのは、「食べる」という行為の奥行きと、他者とのつながりのかたちです。

スープは、誰かを想う“ケア”の料理
哲学者・永井玲衣さんは、全国各地を巡りながら「手のひらサイズの問い」を携えて、対話の場をひらいている。週の半分以上は東京以外の土地で過ごすという日々。そのなかで、ときにスープに助けられることがあるという。
「移動と現場の往復でバタバタしていると、食事をとりそびれてしまうこともあって。そんなときに自宅に帰ってからスープを作って食べると、すごく安心します。『これを食べれば大丈夫』といったおまじないのようなものです」
永井さんは、友人が作ってくれた一皿をきっかけに、スープは“ケア”の役割がある料理なのではないかと考えるようになったという。
「自宅に友人が集まり一緒に作業をしていたときのこと。原稿の締め切りに追われてボロボロになっていた私に、友人が温かいスープを作ってくれて、食べる私の姿を見守ってくれたんです。冷蔵庫にあるものを適当に入れただけのなんでもないスープだったのですが、それがすごく忘れられなくて。きっと友人は『お腹をあたためて』、『これで元気になって』など色々な願いをこめてスープを煮込んでくれたのだと思います。
そういえば、臨床心理士の東畑開人さんの著書に『ケアとは、傷つけないことである』といった言葉があります。がっつりとした味付けでエネルギーを補うような食事もあれば、スープのようにすっと体に寄り添ってくれる料理もある。スープは胃や身体を傷つけない。そういった“ケア”の役割が、スープにはあるんじゃないでしょうか」

さらにスープには、「対話」にも通じる力があるのではないかと、永井さんは考えている。
誰かと食事を囲む時間は、言葉を交わす前の準備のようなもの。スープを前にした食卓が、自然と会話を生むこともある。
「今の社会では、誰かと食事を囲む時間が、少しずつ減ってきているように思います。私は対話をテーマに活動していますが、食を通じて人が集まることには、やはり大きな意味があると感じています。特にスープは、誰かのために作るという場面が自然と生まれやすい料理ではないかなと。以前、友人が私のためにスープを作って、食べている私を見守ってくれていたのも、きっと食卓を囲むという行為だったのだと思います。そうした時間を、スープという料理が、もう一度取り戻してくれるのではないでしょうか」
誰かを想ってスープを作り、共に食卓を囲む。具体的な言葉のやり取りがなくとも伝えられる“ケア”の気持ちが、スープには込められてるのかもしれない。

永井玲衣
哲学者。人びとと考えあう場である哲学対話を全国で開く。せんそうについて表現を通して対話する写真家・八木咲とのユニット「せんそうってプロジェクト」、Gotch主催のムーブメントD2021などでも活動。著書に『さみしくてごめん』『水中の哲学者たち』『世界の適切な保存』。